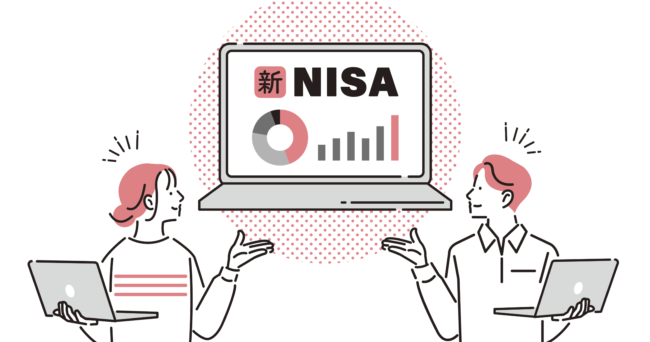毎月分配金を支払うタイプの投資信託を課税口座で購入し、毎月分配金を受取ると、分配金の出ない投資信託を定期的に解約する場合に比べて1,000万円の運用で年6万円の損になります。これは年率3%の運用が一ヶ月定率複利で継続できる場合の試算ですので、リスクのある投資信託では実際にその通りになりませんが、理論的に考える必要があります。お客様に不利益になることが指摘されても平気で放置し続けられる金融業界の「常識」を疑います。
現場への理解と金融制度、金融機関のあるべき姿
資産運用立国議員連盟から今後の我が国の資産運用についての前向きな提案がされている中に、プラチナNISAを創設、65歳以上の高齢者の皆さんに配慮した毎月分配型投信の活用も可能とした制度が提案されているようです。まず、この提言に絡んでお伝えしたい点を確認します。
前向きな良い提案がされることを歓迎する一方、注意して検討いただきたいことがあります。一つはNISA制度が複雑になることで管理がより難しくならないようにして頂きたいこと、二つ目は、金融機関、そしてその職員への指導教育を抜本的に行うべきこと、三つ目は毎月分配金投信についての誤解を生じさせないことです。
NISA制度のあるべき姿
一点目は、現行のつみたて投資枠、成長投資枠の管理の難しさです。投資対象に制限がかかり、使える投資信託が異なることで、パフォーマンスを追求するためには銘柄数が増えすぎるため管理が大変です。
そして、成長投資枠においても積立は出来、マーケットが下がった時にスポットで自由に追加投資が出来るのに対し、つみたて投資枠において、追加投資は自由には行えないといった違いも管理面で不自由。投資はもっと自由であるべきと考えます。
さらにプラチナ投資枠ともなるととても大変になる予感しかありません。より抜本的な制度を一本化する中で、高齢者にも寄り添える制度は、金融業界を挙げ金融制度全体の見直しの中で取り組んでいただきたいところです。NISAについては全体の制度整備をした上で、つみたて投資枠などといった不自由な制度もやめ抜本的な改正を望みます。
現場への理解不足と必要な現場教育
金融機関、そしてその職員への指導教育を抜本的に行うべき点について、国を挙げて認識し、制度の整備と並行して行うべきです。いくら良い制度を作っても、担い手がいなければ本当の意味での活性化とはなりません。
日本証券業協会が発表しているあっせん事例を見ると、仕組債に関したあっせんがいまだに山の様に報告されています。ずいぶん前に実質販売停止状態のはずですが、どれだけでたらめな提案をしてきたか一目瞭然です。
金融の仕事に携わる者がお客様の状況、判断能力等をしっかりと把握せず、自分たちの利益を優先して営業した結果がはっきりと表れています。金融機関職員としてお客様のファイナンシャルプランをしっかりと理解して提案するという、本来、極基本的な動作が実行されていません。資格制度、研修制度の徹底、適合性の原則に反した場合の罰則制度など根本から見直さない限り何も良くならないのではと思います。
スイッチングにおいて、現場を知らない空虚な議論に終始しているところは大きな問題を見過ごしています。
投資信託を買い替えることを営業マンが提案する際、投資信託乗換記録の作成が義務付けられていますが、この作業には一人のお客様当たり1時間程度は必要です。マーケットの急変時に債券運用の投資信託を売却して株式で運用する投資信託を購入する、またはその逆といった提案は、実務上提案自体できなくなっている現状をご存知でしょうか。
また、ポートフォリオで管理していると多くの場合リバランスについてお客様と相談すべきなのですが、これも「投資信託の乗換勧誘」に該当するとされるため、書類作成や申請の必要時間を考えると実質的にできない状態を監督官庁が作り出しています。一人の営業マンが数人のお客様に提案しようと考えた段階で、一日の仕事が終わってしまうような制度運営は誰のためのものでしょう。
そういった不適切な制度運用となっていることに対し、金融機関から真剣に声が上がらないところからすると、そもそもポートフォリオ管理という発想がないか、出来ていない、もしくは、お客様としっかり相談し良い投資信託をチョイスして個別にポートフォリを組めば、ラップよりもはるかに良い運用成績をもたらすことが出来るにもかかわらず、手数料の高いラップの販売ノルマがきついかのいずれかでしょうか。
そもそもの教育が出来ていない上に、現場を理解せず、真に投資家に対して行うべき大切な提案をも出来なくしてしまっている現状です。このことは、当局、自主規制機関といった監督すべき立場の機関が、国民一人一人の利益よりも、自分たちの立場と金融機関を守ることに終始しているようにも見えてしまいます。
そもそも手数料稼ぎの為に投資信託を訳の分からない理由で入替提案をし、顧客の利益を搾取し続けた業界の体質の問題ではありますが、ルールの運用方法により、お客様の利益を害する側面についてどれだけ議論されているのか検証が必要です。これも、抜本的な教育と信賞必罰を怠っている結果でもあると思考えます。
プラチナNISA構想の毎月分配金投信の見直しから想起すること
金融機関は公器でもあるべきと考えますが、現状そのような機能はしているのでしょうか。かねてから指摘されている毎月分配金を受取る投資信託に変えて、定期解約などで対応すべきところですが、ほとんどの業者が対応できていません。
そもそも、金融に携わる皆さんの中にも、誤解している人や仕組みをしっかりと理解してない、もしくは考えようともしない人が多いのかもしれません。投資信託の分配金を受取ることは、投資資金の運用資産の一部を引き出すことになります。通常、課税金額は分配金で受取ると高く、部分解約すると少なくすむため、課税口座においては、部分解約が絶対的に有利となります。
冒頭にご説明した様に、明らかに不利な仕組みの商品を課税口座においても提案し続けている現状において、プラチナNISAといった制度で販売しやすくすることの弊害には注意いただきたいところです。非課税口座で毎月分配金の出る投資信託を保有すること自体には大きなデメリットは無いものの、課税口座では明らかなデメリットとなる点、理解した上で必要があれば制度設計をお進め頂くと良いと思います。
毎月分配型の投資信託は、一般的に手数料、信託報酬が高めなので、インデックス投信などの実入りの少ない商品に入替、定期売却されたら何の商売にもならないからでしょうか。本来、手数料など業者が受け取る利益は付加価値があって初めて得るべきと思うのですが、短絡的に目先のコストと利益を天秤にかけ、顧客利益を無視しているとしか考えられません。
中小など、本当にコストをかけられない業者がすくなくないのなら、こういうところには税金を使ってシステム導入を促しても良さそうに思います。定期解約ができるシステムを導入することでお客様の利益を守って頂きたいところです。
明らかにお客様にとって不利となることを、平気で続けられる業界に繁栄はないでしょう。
今後の議論において、毎月分配金を受取る投資信託が、あたかも有利な投資信託であるといった誤解を生まないようにしていただきたいと考えます。下記に私が2026年1月末に提出し、ある団体のサイトにて公開いただいた内容を、当該団体の許可をいただきこちらにも公開させていただきます。尚、若干加筆修正しております。
毎月分配型投信は買わない、持たない
毎月分配型投信とは、投資家に毎月一定の分配金を支払う投資信託です。安定した収入源としての魅力から、多くの投資家に人気があります。その一方で、毎月分配型投信にはいくつかのデメリットが存在します。今回は、毎月分配型投信の仕組みとそのデメリットについて詳しく解説し、皆様が注意すべきポイントをお伝えします。
投資信託の分配金を受け取ることは非合理的
分配金を受取ることは、投資信託を購入する際、支払った手数料に対し、投資成果について、分配金を受け取った金額分に対して放棄することになります。また、課税口座で保有する投資信託においては、一定の金額を受取る際、分配金として受け取ると税金の支払い分手取りが目減りするのに対し、一部解約して受け取ると節税できます。
手数料を支払って購入する投資信託、課税口座で購入する投資信託は、可能な限り分配金が出ない、売却益で値上がり益を享受できるタイプの投資信託の購入をお勧めします。無駄な手数料や税金を払っていることに気付いていないなら、すぐに改めるべきです。
同じ運用会社、運用対象、ファンドマネージャーが運用する複数の投資信託(ベビーファンド)は一つの投資信託(マザーファンド)としてまとめて運用されていることが多くあります。同じような銘柄名で、毎月分配コース、年1回決算コースとあると、毎月分配金コースではなく、分配金を出さないファンドが多い、年1回決算コースを選びましょう。(中には年1回分配金を支払ってしまうファンドもあります)
毎月分配金を受取ることの非合理性を、理解できない金融関係者はいまだに多く存在し、がっかりすることが少なくありません。投資信託の基準価額の求め方と、分配金を支払うことによる基準価額の変化、投資信託から分配金を受取るときに税金がかかるか否かによる影響を理解しておきたいものです。
もちろん、運用会社の方針で、分配金を出さざるを得ず、かつ、他の投資信託と比べて運用成績の良い商品も少なくありませんので、絶対的に分配金が出る投資信託を否定するわけではありません。ただなんとなく分配金を受取ると儲かっているような気がするとか、分配金が出ていることで安心して、運用状況をよく確認しない皆さんには、基本的な投資信託のしくみを理解していただきたいと思います。
唯一、解約よりも分配金受取が有利なケース
すべてにおいて分配金を受取るコースを選択することが間違いではなく、非課税口座内での投資で、解約時に信託財産留保額が差し引かれる場合のみ、解約よりも分配金受取が有利になるケースがあります。
当然、ずっと上がり続けているときに分配金を受取ってしまうともったいないので、分配金も、解約もせずに大きく育てたうえで途中から解約により少しずつ受取ることができる様、分配金の出ない投資信託を選択するべきではあります。スイッチングといって、全く同じ運用をしている投資信託間でチェンジできる場合には、途中から分配金受取コースに変更する選択肢があり、非課税口座内でできる場合は良いでしょう。ただし、非課税枠を使い切っていると課税口座でしか購入できなくなることも考えられ、投資可能額、取引のある証券口座での取扱い不可等に注意は必要です。
一方で、最初から少しずつ、預けたお金を原資に、分配金を受取るか解約するかを選択する必要がある場合、非課税口座内で比較すると課税によるロスがどちらもありませんので、信託財産留保額がなければ同じ。引かれるのであれば、分配金での受取りが有利となります。
投資信託の基準価額についての基本
国内証券会社などで販売されている一般的な投資信託において、投資信託の値段である基準価額は、一日に一つだけ算出されます。投資対象のマーケットでの一日の終値をベースに、一つの投資信託全体の純資産総額を計算し、その時点で投資家が保有している総口数で割った価格を、1万口当たりで表しています。

この算出の前提として、信託報酬を引いた後の値段となっていますが、表示されている基準価額や、投資成果から、信託報酬分を指しい引いて考えると思い込んでいる人は少なくありません。インデックスファンドより成績の良いアクティブファンドであっても、信託報酬が高いからすべてダメと話している人の中にも、基本的な勘違いをしている人が少なくありませんのでご注意ください。
さて、分配金を支払うと、純資産総額は払った分だけ減ります。そのことは総口数が変わらなければ、その分、基準価額は下がります。分配金を受取った時に、購入価額より値上がった分に対しては、20.315%の税金が、課税口座に預けている投資信託からは引かれます。
毎月分配型投信は、元本を吐き出して分配している商品が多く、基準価額が安くなっている商品が少なくありません。1万口当たりの単価が安いからと言って、組み入れ対象の有価証券が値上がった時に、価格が安くなった毎月分配型の投資信託の方が、同じ運用内容の分配金を出さない投資信託よりも値上がると信じている専門家までいます。
本当にびっくりするような誤解があるのです。これも基準価額の計算方法をしっかり理解していないから生じる間違いですので、基本的な知識を持っておくことはとても大切です。同じ運用内容であれば、値下がり率、値上がり率に大きな差は出ませんので誤解のないようご注意ください。
投資信託の分配金と税金について、一部売却との比較
例えば、毎月10,000円の元本に対し25円ちょうど値上がりし、元本に対して、年率3%ちょうどを分配する投資信託があるとします。この受け取り方をすると受け取った金額の100%すべてが課税対象となりますので、毎月25円の20.315%分、5円少々分税金で持って行かれることになります。
一方、こちらも実際には存在しませんが、定率で値上りを続ける投資信託で分配金が出ない商品を購入したとします。1ヶ月に1万円に対して25円値上がることは、分配金を受取らず運用を続けるので複利効果があり、1ヶ月複利で3%の運用は、年率3.04%程度の年複利運用成果となります。
同じ運用内容の投資信託の分配金受取コースと、分配金を出さないコースとの比較を、課税口座で購入した前提で比較してみましょう。上記の値上がりをずっと続けることになった場合に、元金にどのような差が出るのか、ここでは、買付手数料はゼロとして考えます。
まず、1,000万円購入し、10,000円あたり毎月25円の分配金を受取ると、1,000万円に対し税引き前25,000円、20.315%税金を引くと19,921円と計算できました。この分配金と同額の売却代金手取り額を受取れる、解約口数を計算して、毎月残高口数がいくらで、評価額がいくらになるかを毎月計算しなおす前提で表にまとめてみました。

毎月分配金を受取る投資信託だと元本は毎月決算日に1,000万円となるのに対し、分配金の出ない投資信託での定期解約だと、1年で6万円増える計算となります。毎月分配型定期解約後の残高評価額の推移をご確認下さい。
毎月分配金として受け取ると、決算日については、分配金受取コースの基準価額は永久に10,000円、1,000万円投資した元本は永久に1,000万円となる前提となります。これに対して分配金の出ない投資信託は、1年経過時点で10,304円、10年で13,494円、30年で24,568円と値上りを続けることになります。
毎月、19,921円を受取るために必要な売却口数はだんだん少なくてよくなります。一方で、定期解約時に必要な税金は、当初1カ月目は10円で済むのですが、1年目で100円、10年目は1,106円と計算されます。分配金で受取ると全額の20.315%引かれた金額が手取りになるのに対して、一部解約すると値上り率が高くない間は、売価代金全額に対する税率はとても低く、10年目でも実質5.55%と少なくて済みます。
一方、毎月分配で受取る場合の必要税額は、常に計算上5,079円となります。このことは、投資信託に残せる残高(純資産額の本人持分)が絶対的に定期解約の方が多く、有利となります。
この影響は大変大きく、仮に100年保有しても、200年保有しても、分配金受取時の20.315%を超えることはありません(もちろん限りなく近づきます)。同じ税引き後の金額を受けとりながら運用を継続する場合、分配金を受取るよりも、かなり多くの金額を元金として運用できることになります。
投資信託の元本部分を1円でも多く残すことは、ずっと値上がることを前提で考えると、大変重要なこととなりますので、資産を少しで増やしたいのであれば、可能な限り分配型投資信託の購入は避けるべきです。1,000万円の投資において、1年で6万円、10年で63万円、20年で134万円、30年で219万円以上の金額分、解約での対応の方がお金を多く残せる計算となります。
子、孫の代まで投資信託のまま引継ぐ前提で考えれば、50年後は460万円、100年後は2,177万円、200年後には4億3,698万円ほどの差と計算できます。節税と、福利での運用の力はとても大きいですね。投資する意義や、ご自身の考えを伝えながら、インフレ負けしない資産運用管理と、投資を通じた社会貢献などの大切さを伝える大人の投資家として考えてみて下さい。
どこでも対応してくれるわけではない定期売却サービス
毎月分配金を受取るのは手間がかからないけど、毎月売却するのは面倒です。そこで、一部の証券会社では、定期売却のサービスを始めています。金額を指定して売却、割合を指定して売却、期間を指定して、等口数に分割して受け取るなど、業者により対応は異なります。
ネット証券でも売却はできるが自動的な任意の銀行への振り込みはしてくれないなど、思ったような対応が出来ないところも多いかもしれません。こういったサービスの中で、よりお客様寄りのサービスを受けられる金融機関、方法もありますので、必要でしたらお問い合わせください。
投資信託への投資は、もちろん元金が大きく目減りすることもありますので、長期的な視野に立って商品選択、ポートフォリオ構築をしていく必要があります。利益部分のみ受取るならまだしも、元本部分まで分配金として払出してしまう投資信託など、「まがいもの」として考えるべきで、選択の余地はありません。
投資には、ご自身のお考えを実現するためや、利益を膨らませるために資金を振り向けると思いますが、入り口で必要以上に手数料を取られたり、余計な税金を多く取られたり、ロジックからして皆様にとって有利ではない提案があまりにも多いと感じています。情報があふれる中で、何が理論的に正しいのか、しっかり確認頂く事をお勧めします。